- シーンから探す
-
贈る相手から探す
- 彼氏
- 彼女
- 男友達
- 女友達
- 夫・旦那
- 妻・奥さん
- お父さん・父
- お母さん・母
- 両親
- おじいちゃん・祖父
- おばあちゃん・祖母
- 女性
- 男性・メンズ
- 妊婦
- 同僚
- 同僚(男)
- 同僚(女)
- 上司(男)
- 上司(女)
- 部下
- ビジネスパートナー・取引先
- 夫婦
- カップル
- 親友
- 女の子
- 子供
- 男の子
- 赤ちゃん・ベビー
- 乳幼児
- 1歳の誕生日プレゼント
- 2歳の誕生日プレゼント
- 3歳の誕生日プレゼント
- 4歳の誕生日プレゼント
- 5歳の誕生日プレゼント
- 6歳の誕生日プレゼント
- 7歳の誕生日プレゼント
- 8歳の誕生日プレゼント
- 9歳の誕生日プレゼント
- 10歳の誕生日プレゼント
- 18歳の誕生日プレゼント
- 19歳の誕生日プレゼント
- 20歳の誕生日プレゼント
- 21歳の誕生日プレゼント
- 22歳の誕生日プレゼント
- 25歳の誕生日プレゼント
- 26歳の誕生日プレゼント
- 30歳の誕生日プレゼント
- 40歳の誕生日プレゼント
- 50歳の誕生日プレゼント
- 60歳の誕生日プレゼント
- 70歳の誕生日プレゼント
- 80歳の誕生日プレゼント
- 88歳の誕生日プレゼント
- 90歳の誕生日プレゼント
-
カテゴリから探す
- 名入れギフト
- 記念品
- 文房具
- 花
- ビューティー
- こだわりグルメ
- ジュース・ドリンク
- お酒
- 絶品スイーツ
- ケーキ
- お菓子
- プリン
- フルーツギフト
- リラックスグッズ
- アロマグッズ
- コスメ
- デパコス
- インテリア
- キッチン・食器
- グラス
- 家電
- ファッション
- アクセサリー
- バッグ・ファッション小物
- ブランド腕時計(メンズ)
- ブランド腕時計(レディース)
- ベビーグッズ
- キッズ・マタニティ
- カタログギフト
- 体験ギフト
- 旅行・チケット
- ダレスグギフト
- ペット・ペットグッズ
- 面白い
- 大人向けのプレゼント
- 贅沢なプレゼント
- その他ギフト
- プレゼント交換
- 絆ギフト券プロジェクト
- リモート接待・5000円以下
- リモート接待・8000円以下
- リモート接待・10000円以下
- リモート接待・10000円以上
- おまとめ注文・法人のお客様
●江戸和本●賀茂長明 方丈記諺解 鴨長明方丈記諺解 摂陽山人 元禄 随筆注釈
-
商品説明・詳細
-
送料・お届け
商品情報
残り 1 点 8,500円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月13日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
-
ラッピング
対応決済方法
- クレジットカード
-

- コンビニ前払い決済
-

- 代金引換
- 商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
- ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
-
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行 - Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)
-















](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m81929331082_1.jpg)


](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m87968076128_1.jpg)





![値下げ[サイン!初版!美本]開高健『歩く影たち』川端康成文学賞 署名 昭54初帯](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m24505291896_1.jpg)

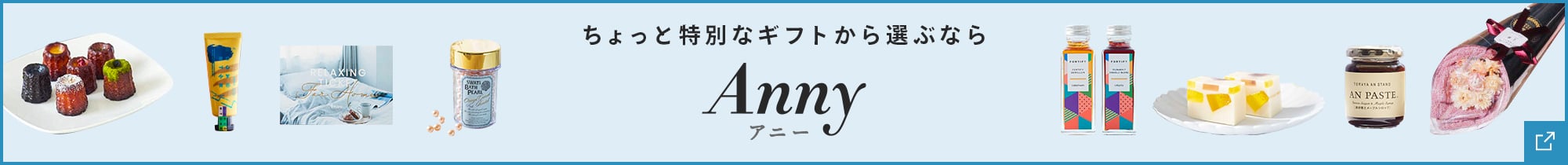




〈賀茂長明〉方丈記諺解[鴨長明方丈記諺解]
【判型】半紙本2巻1冊。縦220粍。
【作者】摂陽山人作。
【年代等】元禄7年2月初刊([大阪]清兵衛ほか原板)。江戸後期後印。刊行者不明。
【備考】分類「随筆・注釈」。『方丈記』の注釈書。『方丈記』の本格的な注釈研究は、江戸時代の明暦期以降で、山岡元隣『首書方丈記』と大和田気求『方丈記説(チセツ)』が明暦4年(1658)刊行され、続いて、加藤磐斎『長明方丈記抄』が延宝2年(1674)に、著者未詳の『方丈記諺解』が元録7年(1694)に、さらに、槙島昭武『方丈記流水抄』が享保4年(1719)に刊行された(『方丈記』注釈書の近世刊本は以上5種)。そのほか、未刊であるが仁木宜春『方丈記宜春抄』(元録9年作)という写本もある。このうち『方丈記諺解』は、上下2巻からなり、上巻見返しに「鴨御祖社系図」を、続いて、著者および書名の解題(「鴨」「長明」「方丈」「記」に分けて解説)を掲げ、上巻末に「鴨長明方丈記諺解巻世間」、下巻末に「鴨長明方丈記諺解巻出世」と記すように、上巻を出家前の長明、下巻を出家後の長明の作として捉えて、『方丈記』の本文を大字・半丁4-5行で掲げ、細字の傍注のほかに長文の解説文を付す。冒頭の系図は『首書』や『説』にはなく、『方丈記抄』では47名の人名が載るのに対して『諺解』は27名とやや簡略化されている。解題は先行書の何れにも載るが、『諺解』は『首書』に似通っている。さらに本文の注釈は、『首書』や『説』の如き頭注形式を採らず、大字本文の所々に線引きして簡潔な傍注を記すため、身安く、分かりやすい。このほか、本文を細かく区切って補足説明や多彩な評言からなる解説文は、流麗な雅文で綴られ、解説文自体が一種の文芸作品の様相を呈しており、この点は先行する『方丈記』注釈書にない特長である。『方丈記諺解』は、「最初の注釈書である『首書方丈記』を大いに活用しつつ、頭注形式を採らずに、本文を短く区切ってその後に評論的な解説文を書くことによって、それまでの注釈書と比べて、各段に自由で伸びやかな、それ自体が随筆的な評論であるような、新たな注釈書の方向性を打ち出した」ものといえよう(島内裕子「『方丈記諺解』の注釈態度」参照)。
★原装・題簽欠・状態概ね良好(表紙やや汚損・本文一部小虫)。